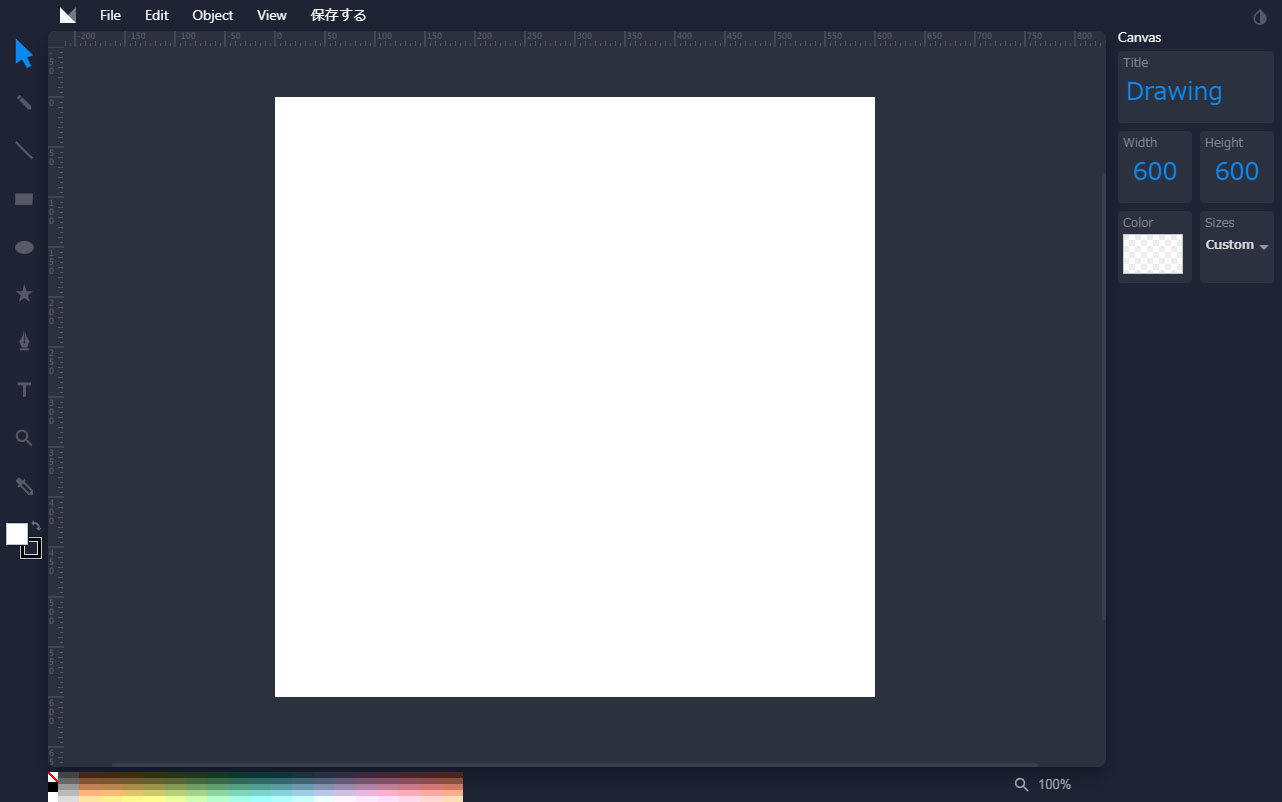夜ののれん屋ポルタに、湯気をまとった番台のおじさんが入ってきた。
作務衣姿にタオルを肩にかけ、声はやたらと張りがある。
「こんばんは。銭湯の入口に掛けるのれんを新しくしたいんだが、
正直、普通の『ゆ』じゃもう誰も驚かんのよ」
店主は静かに微笑んだ。
「では、お客さんを驚かせたい、と?」
「そう! のれんを見ただけで“お、ここは違うぞ”って思わせたいんだ」
カウンターの端で、おもちが耳をぴょこんと立てる。
「じゃあ“ぬ”にしてみませんか? 逆さにすれば“ゆ”っぽく見えますし」
おじさんは目を丸くした。
「ぬ……!? いやいや、誰も読めんだろう」
「でも、のれんをくぐって湯船に浸かれば、結局“ゆ”ですからね」
おもちの言葉に、店主は小さく笑った。
「なるほど。では、『ゆ』をわざと逆さに染めましょう。
初めて見る人は戸惑うでしょうが、常連には合図のようになるはずです」
おじさんは腕を組み、にやりと笑った。
「いいな、それ。ウチらしい悪ふざけだ」
数日後。
出来上がったのれんを受け取りに来たおじさんは、布を広げて大笑いした。
藍色の布に白抜きで大きな「ゆ」――ただし逆さ。
風に揺れると、まるで水面に映った文字がゆらいでいるように見える。
「これは……お客、絶対ざわつくぞ!」
店主は穏やかに言った。
「のれんは境目を示します。ときには“違和感”こそ、人を引き寄せるのです」
おもちはにっこりしてつぶやいた。
「間違えて“ぬ”って読んだ人は、そのままぬるいお湯にどうぞ」
おじさんは腹を抱えて笑い、のれんを持って帰っていった。
カラン、と鈴の音が鳴る。
次のお客が、のれんをくぐってきた。